今こそ読書
20−06 2020.10.2
コロナの初期の行政や学校のちぐはぐな対応を見ながら思ったものです。子どもたちには、もうしばらく授業はいいから、今こそ「読書」させたら良いじゃないか。もちろん、ここまで長引くと学校制度やそれに対応する措置が必要で大変この上ないことは承知しています。しかし、まとまった時間でしか読めない本とかがあるのではないか、と思ったものです。私はほんの少しだけ実践出来ました。
「百年の孤独」

私がもっぱら世界文学を読んでいたのは約30年前の高校時代から大学入学初期にかけてのことですが、どうしても文庫で買うか、近くの図書館で借りるかということでしたから、インターネットもない高校生の行動範囲の中にはガルシア・マルケスの作品はまだ見当たらず、名前だけなんとなく知っているという状態だったのでした。その後、大人になって本を読まなくなっても、たまの休日(ほとんどないが)や何かの記念日には自分自身で本を買う習慣があるのですが、2、3年前に買った本の中に、大学時代に読み損ねていたガルシア・マルケスの名著「百年の孤独」があって、さらにそのまま「つんどく」されていたのです。しかし、この自粛期間に思い切って読むことが出来ました。マルセル・プルーストの小説なんかと一緒で、一定の時間がないと読むことが困難(何しろ、登場人物の名前が一緒なので、家族の系譜なんかを確認しながら読む必要がある)な作品だと思いますが、これが本当に素晴らしく、「自分の人生が、ガルシア・マルケスを読んでない人生でなくて良かった」と心の底から思いました。もちろん、それは「ドストエフスキーを読むことは当然である 」「ヘルマンヘッセを読むことは当然である」という前提に立っています。その上で「内容を詳細に覚えていないとしても、マルセル・プルーストを読んでいることは、表現者としての自分の人生に少し自信が持てる」「ロマン・ロランを読んでいることは、同世代以下よりは会話内容に厚みを付けられる」云々、と考えてきたのですが、「ガルシア・マルケス」の痛快さ、荒唐無稽さ、訳の分からなさ、はやはりは西欧文化芸術とは一線を画すようにも思い、そういう意味でも「ガルシア・マルケスを読んでいる人生で良かった。これを読んだことで世界観が広がった」と思いました。「イタリアやドイツやフランス旅行」に対して「アマゾンのジャングルにも行った」というイメージでしょうか。たかだか本を読んだということではありますが、世界観、人生観に対する諸相を知ることになり、それまでの自分自身に対して「世界はもっと広く、文学や芸術はもっと豊かだったんだ」という感覚や気持ちを持つことが出来ました。
趣が異なるので、好き嫌いはあるでしょうが、私は、そのエネルギーに圧倒されたという訳です。セットで読んだ短編の「エレンディラ」「世界で一番美しい水死人」だけでも何というか超越的でした。「なるほど、こういうのありなんだ」ということでしょうか。今は「コレラ時代の愛」が読めればと思っているところです。
「平家物語」

必要あって平家物語の一部分を読んだのですが、恐らくひと昔前の日本人なら「誰でも知っている逸話(例えば「青葉の笛」など)」について、私も知らなかったことが多く、きっと今ではすっかり知られていない逸話もたくさんあるのだろうな、ということに気づきました。グローバルな時代になり、情報が溢れ返っているわけですから「淘汰」されてしまうのは時代の流れだとしても、やはり古典や古いものを「教養」として身に着けることは大事だな、と思うのです。若い人たちが「唱歌や民謡を知らない」というときに、「そりゃ時代だな…、という話ではなく、ちゃんと教養として知っておこう」という話をよくするのですが、自分自身も教養としてのもろもろを備えておくことが、文化芸術の審美眼、考え方、社会的な判断の基軸を持つことにも繋がる、と思っています。平家物語の心を打つ美しい台詞は「1Q84」にすら出てきて(「ふかえり」が朗誦して)ますからね。作家の手法として、あのセリフを切り取りたくなる気持ちは分かりますね。
村上春樹ばかりを読む人には、村上春樹はドストエフスキーや平家物語を呼んでいるということ、信長貴富ばかりを聞く人には、信長貴富はバッハやモーツァルトを聞いているということを言いたくなることがあります。もちろん興味の持ち方は自由なのですが、その根元にある大地が重要だという意味において。
「夜長姫と耳男」「桜の森満開の下」


私の青春は劇団「夢の遊眠社」が一世を風靡していた頃と重なりますが、あの手の演劇は東京から離れるて過ごしていると生で見ることの出来る機会が極端に少なくなるので、結局、「見たいな」と思いながらも生で見たことはありませんでした。最近になってビデオやDVDで遊眠社の作品を見たり、NodaMapの作品を見る機会がありましたが、ようやく「贋作:桜の森満開の下」を見た影響で、家にあった坂口安吾の文庫を読み直すことになりました。読んだはずなのに何故かほとんど覚えておらず、やはり読書というものには、自身の心境やタイミングや環境や年齢が重要だと感じました。読まないより読んだほうが良いのですが、いろんなタイミングで読んでみると突き刺さり方が違うということでしょうか。ああ、もう少し落ち着いて読んでいたなら、きっとこの作品は私の胸を支配続けていたでしょう。特に「夜長姫と耳男」のほうですねえ。恐ろしい凄みと愛の怖さ(淀川長治ふう)を実感させる傑作ですねえ。
「チェーホフ短編集」
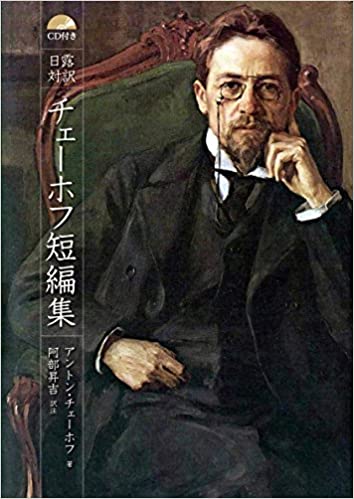
これは少し前に新訳で読んでいたものを、もう少し読んだということでもあります。この再びの読書は「時代による訳の違い」を深く考えさせられるものになりました。もちろん、内容面も「大人の恋や大人の心境の機微」が書かれているものも多く、旧訳で読んでいたときには私は18歳くらいだったわけですから、「読むのが早すぎたために表面的にしか理解出来てなかった」としみじみ思いました。もう一点感じたのは、やはり日本語訳が50年以上違うと、随分言葉遣いも変わり、感覚も変わるということなのです。
もちろん一長一短があって、外国の唱歌の日本語訳出や賛美歌の訳の問題とかぶります。例えば、原作も古典なわけですから、ある種の格調高さや言語を吟じるような感覚が必要な場面があるかもしれません。しかし、旧訳ならなかなか文体にひっかかって読めなかったものが、多少の軽さやカジュアルさがあったとしても、新訳では読む気になれたり、リアルに受け止められたのだとしたら、そのほうが良いということもあろうかと思います。
歌の話ですと、個人的な感覚ですが、例えば「春の日の花と輝く」や「蛍の光」なんかは、意味が分かりにくくともそのままの日本語訳で教えたい気持ちになります。つまり、古くて意味が分かりにくくても音韻や語感が美しいと感じる曲なんかはそのままで歌わせたいと思うのです。ただ、「庭の千草」も出だしの「にわのーちーぐーさーも」には美しいメリスマがあるのに「むーしーのねーも」は母音の種類も含めて歌わせにくいし、語感がものたりないと感じます。そもそも、メインのところが<あーあしーらーぎーく>ではちょっと…と思ったりしておりましたし、「ダニーボーイ」も、「いとしのなれを、ちちぎみのかたみとし」というのはちょっと封建的すぎる言い回しのように感じ、私自身による新しい日本語歌詞を作って歌って(歌わせて)おります。例えば、「庭の千草(これは「夏の最後の薔薇」として)「ダニーボーイ」「ロッホローモンド」「アニーローリー」なんかの太古の訳に対しては新しい歌詞を与えている途上なのです。
もちろん私の取り組みと比較するつもりはありませんが、例えば、亀山郁夫氏の訳がなければドストエフスキーは古典中の古典になってしまい、今よりも読まれてなかったでしょうし、チェーホフも沼野充義氏の新訳がなければ、私も再読しなかった訳です。ある種の古風な品位を保ったままで、日本語の見直しもしながら良いものを引き継ぐ努力をしていくことも大事なのではないかな、と考えた次第です。
ちなみに、ちょっと必要があってラフカディオ・ハーンの「KWAIDAN」を二人の訳で読み比べていたのですが、それぞれに「なるほどな」と思うことばかりでした。
「星を継ぐもの」

珍しくある店で順番を待っている間に読んでいたのですが、もっともらしい科学的記載が続き、リアリティを持たせたまま(とてつもない方向へ)と展開していく話法に引き込まれました。何よりスケールの大きすぎる発想力に圧倒されました。特にSFというジャンルを意識することはありません。何しろ私が無人島に持っていく1冊はきっとレイ・ブラッドベリの「火星年代記」やスタニスワフ・レムの「ソラリス」になるでしょうから。
同時に「タイタンの妖女」も読みました。なんとも「目が回って凄かった」としか言えませんが、最後にはほろりとさせられました。ともに強烈なインパクトを心に残しています。
「キャッチャーインザライ」
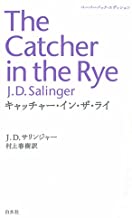
中学生くらいの頃からよく読書感想文等の課題図書に上がっていた気がします。「ライ麦畑で捕まえて」のタイトルは当然知っていたのですが、なんとなく女の子が主役の話かと勘違いし、敬遠してきた記憶があります。話の筋等がいろんなものに引用されたりしているので、そのうちにそれとなく知識として内容を理解してからも、「いざ読書」とまではいかなかったのです。
話は変わりますが、ある時「みやこキッズハーモニー」のスタッフから唱歌(スコットランド民謡が原曲)の「故郷の空」(ゆうぞら晴れて秋風ふくー)を子供たちに歌わせたい、という声があがりました。実は、そもそもそれは私の好きじゃない曲なので避けて来たのですが、「何故なのか?」と問われ、リクエストが続いたので、つい「いや、そもそも訳が気にいらない、<あき>と音が下がるので歌わせにくい」と言ったところ、「じゃあ訳したら」と言われ、すぐにその気になってしまいました。
で、「故郷の空」に新しい歌詞を付けようとあれこれ調べているうちに、訳としてはややふざけた感じのする「麦畑」(だれかさんとだれかさんが、むーぎばーたけ)のほうが原詩に近いようだ、とか、そもそも原詩は「ライ麦畑」であって、小麦よりも背が高いライ麦であることが歌詞の中身を憶測させやすくしている…、ということが分かってきたのです。さらに調べると、サリンジャーの「ライ麦畑で捕まえて」の主人公は、放浪する途中で通りすがりの少女が歌っているこの歌に癒された…云々と書いてあり、久しぶりにこの書物を読まねばならないことを思い出したのです。
当然「読んでいるべき作品を読んでない」ということはもちろんよくあり、マークトウェインの作品なんかもそうなのですが、まずはこっちをさらっと読んでおかねばと思い、これまた「つんどく」になっていたペーパーバック版(村上春樹訳)を手にしたのでした。
タイトルが、「キャッチャーインザライ」…またまたあ、と思いながら読んでいたのですが、最後まで読んで、ようやく「ライ麦畑で捕まえて」というタイトルは誤訳だという説があったことを思い出しました。確かに読後にその根拠について理解出来ました。しかし他方で訳者が主人公の内的心理まで読み込んだ意訳である、と深く解釈することも出来るのではないかと思ったりもしました。でもまあ、だからこそきっと原題そのままとなった村上訳が懸命なのでしょうねえ。
例の「麦畑」の歌が出てきたところあたりから最終頁に至るまでの畳みかけるような流れと、そのリアリズムに大きな共感を得ました。やはり当然読んでおかねばならない1冊ではありました。やはり、今こそ読書。良かったです。
午後のつぶやき
2021年2020年
・20−01 2020明けました
・20−02 長崎「祈り」の演奏会
・20−03 エレンと時まもりの木
・20−04 コロナ禍の中で
・20−05 頑張れ、大学合唱!
・20−06 今こそ読書
・20−07 なしのはなし
・20−08 2020年振り返り
2019年 (5)
2018年 (9)
2017年 (7)
2016年 (8)
2015年 (11)
2014年 (10)
2013年 (6)
2012年 (18)
2011年 (21)
2010年 (15)
2009年 (15)
2008年 (15)
2007年 (23)
2006年 (4)